校長の声『四旬節』
カトリック教会は季節によって祭服の色を使い分けているが、節制と悔い改めの象徴と見なされている紫を使う時期はクリスマス前のおおよそ4週間の待降節、そして復活祭前の40日間の四旬節である。和洋折衷の祭りで言えば、四旬節は(どんちゃん騒ぎの)節分と(卵探しの)Easter Bunny(イースターのウサギ)と、息抜きのために3月3日のひな祭りが挟まれている期間である。ドイツ語では馬鹿正直に"Fastenzeit"、断食節と呼ばれているが、英語の"Lent"の語源は「春」、ラテン語の"Quadragesima"は40(日)で、具体的に何をするかを定めない期間の名称となっている。
聖書には40日の四旬節と断食を結びつけるいくつかの話があるが、代表的なものとして新約聖書からマルコによる福音の第1章、12節~13節を紹介する。イエスがヨルダン川で洗礼を受けた後の話である。
「それから、"霊"はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは四十日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。」
この最初の四旬節が終わった後、イエスは本格的に神の国を伝える宣教活動を始めたが、我々人間にもやはりこのような期間が必要であろう、砂漠のように荒れ果てた自分の心を見つめ直す四旬節として...
考えてみれば、これは四旬節だけのことではない。整理整頓だけで解決できる問題でもない。自分の成長に繋がる活動を見つけ、人生の限られた時間を有効に使うことは、季節と関係ない継続課題である。


1枚目&2枚目:整理整頓で解決できる問題の具体例二つ

3枚目:カリタスジャパンの「四旬節 愛の募金」ポスター(2018)

 アクセス
アクセス Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ



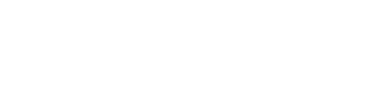


 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ