高校1年生 哲学対話講座「MISONOてつがくサークル」
10月30日、南山大学副学長 人文学部 奥田太郎教授のご指導のもと、高校1年生(77回生)がクラスごとに哲学対話を行いました。
奥田教授は講座のはじめに「哲学対話」の位置づけにふれ、「共通のテーマで会話をするけれども、結論を出したいわけではありません。あえてモヤモヤを残すことで、人間は考え続けることができるからです」と教えてくださいました。

まずは会場のサブアリーナで輪になって、「今日の調子・気分・(いる/ある場合は)自分の"推し"」を1人ずつ簡単に話していきました。奥田教授から
・他の人の声を聴く
・自分の声で話す
・話のオチを先送りする
という「哲学対話のルール」が紹介されたところで、本日のテーマ「人生において"推し"は必要か?」が発表されました。

身近でありながら賛否両論が飛び交いそうなテーマを聞き、77回生の表情に少々緊張が走ります。「意見を戦わせる時間ではありません。無理に交わろうともしなくていいです」とのヒントを奥田教授からいただき、さっそく対話がはじまりました。大切なのは、「対話の前後で、自分に変化があるかどうか」だということです。
対話の時間は90分。
77回生は次々と手を挙げて、自分の意見をしっかりと述べていました。
円形にセッティングされた場の効果もあり、発言者の方へ自分の身体を向けながら、じっくりと相手の声を受けとめる姿が多くみられました。講座終了後に奥田先生へ熱心に質問を投げかける生徒もおり、知的好奇心を大いに刺激される時間となったようです。
「てつがく」を体験させてくださった奥田先生、ありがとうございました!
◆生徒の感想より◆
・「この人を○○年間推している、ずっと応援している」という話が挙がったけれど、熱しやすく冷めやすいことを自覚している私は、"推し"が短期間で変わってしまいます。自分にはない価値観をもち、行動できる人をとてもうらやましく感じました。だからこそ、今日学んだ「哲学では『多種多様』が許される」という考え方に救われています。"推し"について立派な意見はもっていないけれど、ありのままの自分の気持ちを受け入れていくことができたように感じました。
・普段は友達に「調子はどう?」などとは尋ねないので、新鮮な経験でした。今この人はこういう気持ちなのだ、と知ることで自分の接し方も変化してきて、そこが面白いなと感じました。「哲学=決められたものに、決められた答えがある」と考えていましたが、今回の講座を経て「哲学=楽しいもの」というイメージになりました。興味の有無で決めつけず、視野を広くもっていきたいです。
・"推し"という感覚が人間に備わっているからこそ、アイドルやスポーツ選手などの商売が成り立っていて、経済も回るのではないかと感じています。伝統や文化などが廃れずに残っているのも、そこに魅力を感じ、"推して"いた人がずっと繋いできた結果だと思うので、"推し"の感覚は人生において必要であると考えました。
・講座を受けて、少し考え方が変わりました。相手から聞く意見に対して、いつもなら「自分はこう考えているから」と意見を押しつけるように話してしまいます。ですが、今日の対話で相手の意見をしっかりと受け入れる大切さに気づかされました。今後の生活では、意見の相違があることは当たり前なのだということを忘れずにいたいです。
・哲学科に進学するか迷っている私にとって、実りある時間でした。哲学対話のルールについて質問したとき、「意見が被ってしまっても、人それぞれの声で伝えればいい」ということがわかり、緊張していた心が軽くなったように感じています。「推しはある意味でライバルだ」というクラスメイトの発言にもとても納得しました。「推しはこれだけ頑張っているのに、何も頑張らずにいる自分はステージを楽しめる立場なのか」という思いを聴いて、自分が時折感じていたもやもやが言語化されたように感じました。
・「話すこと」「声を聴くこと」の重要性を感じました。今後の人生においても必要なことだと考えています。人と話して意見を言い合うことによって新たな考えが生まれ、そして誰かの疑問が解決する。そんなことを、今回の哲学対話で実感しました。

 アクセス
アクセス Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ


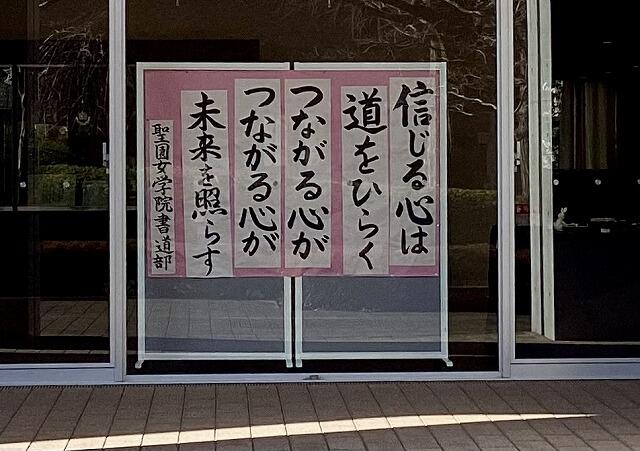
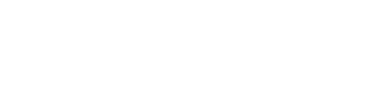


 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ