芸術鑑賞教室
11月20日、鎌倉芸術館にて芸術鑑賞教室「能楽」を行いました。

◆狂言「盆山」
日本庭園のミニチュア版「盆山(ぼんさん)」をたくさん持っているけれどもなかなか譲ってくれない主人の家に、男が盗みに入ります。企みに気づいた主人は、隠れている男にいろいろな動物の真似をさせてからかいます。

シンプルな筋立てでありながら、ユーモアたっぷりの動きや擬音語が次々と登場する作品に、客席からは大きな笑い声も!「古典芸能は難しくてわからない」とのイメージが序盤から崩されていきます。狂言が成立した室町時代、犬の鳴き声(遠吠え)は「びょうびょう」と表現されていたことにも、生徒たちは驚いていました。
◆囃子方紹介
続いて囃子方(はやしかた)が紹介されました。
演奏する楽器が口元に近い順に並ぶことや、雛飾りの「五人囃子」は能の囃子方を模していることなどを教えていただきました。

決められた言葉で拍子をとっており、お互いに姿が見えない状態であっても演奏の息が合うとのことです。

◆能「黒塚」
陸奥・安達ヶ原にたどりついた阿闍梨祐慶と山伏は、人里離れたところで老婆に一夜の宿を求めます。我が家のみすぼらしさを恥じていた老婆でしたが、二人の説得に根負けして部屋へ招き入れます。

老婆は糸繰りの様子を見せつつ世のはかなさを嘆き、「寒くなったから」と薪を採りに山へ入ります。「部屋の奥は決して見ない」という約束を交わしたはずが、破られてしまいます。

老婆は人喰いの鬼でした。

本性を顕わにして二人に迫るものの、最後は調伏されて弱々しく消えていきます。

老婆の豹変ぶりと終盤の激しい調伏の様子に生徒たちは圧倒されました!
劇場のモニターには舞台の進行にあわせて口語訳が映し出され、難しい台詞も理解できる工夫がなされています。
終演後は質疑応答が交わされ、摺り足の技法や普段の練習方法など、演じ手ならではの視点からお答えいただきました。室町時代から受け継がれてきた古典芸能の魅力を垣間見ることができたひとときでした。
〈生徒の感想より〉
・「鬼は鬼になりたくてなったわけではない。誰の心の中にも鬼はいる」という言葉に、善悪ふたつの面がとてもわかりやすく表されていることを感じました。
・「能の家に生まれると、小さいころから稽古漬けの日々」ということを伺い、古典芸能の迫力や受け継がれてきたものの重さを改めて感じました。
・近所にある劇場で古典芸能が演じられていることがあるのを初めて知りました。全く予備知識がなかったものの、予想していたより理解できたのでまた訪れてみたいと思います。
・所作や感情の表し方が美しくて感動しました。ミュージカル舞台をよく観に行きますが、西洋の演劇とはまた違う良さを発見できました。

 アクセス
アクセス Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ
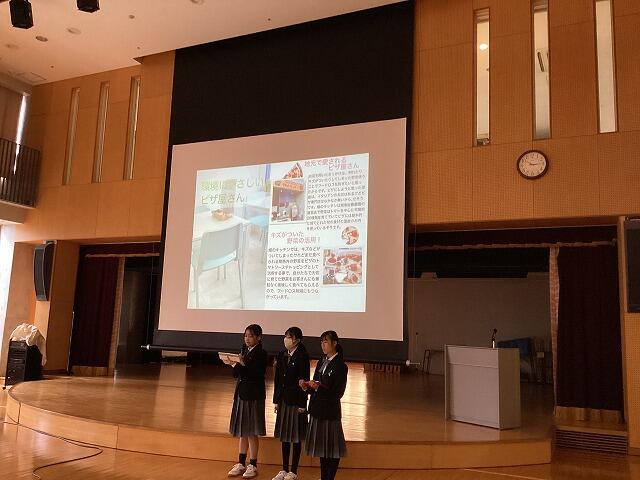


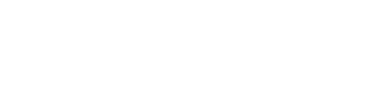


 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ